── ドア・イン・ザ・フェイス?
顔の中に、ドア?
これは、
『shut the door in one’s face』=『門前払い』
の意味を由来に持つテクニックのこと。
── 門前払いされるためのテクニック?!
てか、それ以前に、そんなテクニックって必要?
ね。
おかしなネーミングですよね。
そして『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』に必要なのが、
『初めにわざと門前払いされるようなムリなお願いをすること』
意味不明レベルマックス……
ですが、人の心の動きを知ると、
── なるほど。
『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』、ナイス。
となるはず。
なかなか優秀なテクニックなのです。
今回はこの『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』について。
その意味や由来(は書いてしまいましたが)、参考例などのご紹介です。
なぜ、初めにわざわざ断られるようなムリなお願いをする必要があるのか?
そのことで、何が変わるのか?
ぜひぜひこのテクニックを活用、または応用し、色々な場面でお役立ていただければ、と思います。
『ドア・イン・ザ・フェイス』ってどんなテクニック?>
『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』の別名は『譲歩的要請法』、または『拒否したら譲歩技法』。
『拒否したら譲歩技法』……何と言いますか、これまたすごい名前です。
が、これが一番『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』、そのままの意味を表わしている言葉でもあるんですね。
先ほど書きました通り『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』の最初の一歩は、
『わざとムリなお願いをすること』
とりあえず、何かムリなお願いをしてみましょう。
-
「今回の舞台で、主役をやらせてください!!」
……新人役者さんが、とてつもない野望を願い出ています。
それを受けた舞台監督(が配役を決めるものとして)は、当然断ります。
この時の舞台監督の気持ちは、どのようなものか?
-
「熱意は認める。
だが、悪いがいくら何でもそれはムリだ……」
のような感じだと思います。
そして新人役者さんが『お願い第二弾』をする。
-
「わかりました……
では、せめてどんなチョイ役でもいいので舞台に立たせてください!!」
そしてまた舞台監督の気持ちです。
-
「主役はムリ(に決まってる)だが……
チョイ役くらいなら、まあいいか」
そして新人役者さんは人生初の舞台で『通行人・その4』の役を獲得。
この新人役者さんが使っていたのが『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』です。
もう一度この流れを客観的に見てみましょう。
- 依頼する側: 断られるようなムリな依頼をする
- 依頼を受けた側: 当然断る
- 依頼する側: 初めの依頼を諦め、それよりもハードルを下げたお願いをする
- 依頼を受けた側: 応諾
(※『応諾』: 人の頼みごとを快く引き受けること)
新人役者さんが最初のお願いを拒否され、その後ハードルを下げたお願いに変えたことにより、応諾される、です。
『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』とはこのように、
『初めにわざと門前払いをされるようなムリなお願いをして、その後そのハードルを下げることにより、本来のお願いを受け入れてもらいやすくするテクニック』
のことを指しています。
……『拒否されたら譲歩』、そのままの流れだっていうのはわかったのだが……
どうして受け入られやすくなるのか、その理由がさっぱりわからない……
なぜ新人役者さんはあえて最初にムリなお願いをする必要があったのか?
その後のお願いがすんなり受け入れられたのはなぜか?
今度は『心』の部分から、その理由を見ていってみましょう。
なぜ人は受け入れてしまうのか?

大抵の人は誰かから親切にされたりプレゼントをもらったりすると、何らかのお返しをしたくなるもの。
もらいっぱなしだと、何となくムズムズします。
そこで、
「この前はありがとね。これ、お礼ってほどのものじゃないけど、よかったらみんなで食べて」
などで、ムズムズを解消。
『もらったら、返す』。
このように人が自然に感じる心の働きを利用したテクニックが『ドア・イン・ザ・フェイス』。
では、もらいっぱなしで返さなかったらどうなるか?
『あの人は道徳的に問題のある人だ』
というレッテルを貼られてしまう。
そして、このレッテル、悪いイメージを持たれてしまうと、その後いくら正しい行いをしても、なかなかその印象を覆すことができなくなるのです。
これも『ネガティブ・バイアス』と呼ばれる自然な心理。
だから『もらったら返す』。
『他人から受けた行為と類似する行為を自分も他人に対して行うべき』
こうした人が無意識のうちに持つ自然なルールのことを『返報性の規範(へんぽうせいのきはん)』と呼びます。
(※『返報性の原理』とも)
『類似性の法則』や『ペーシング』などにも、この『返報性』は関係してきます。
『好意の返報性』
『自己開示の返報性』
などですね。
「自分に好意を持ってくれている相手に対し、自分も好意を持つ」
「相手が『相手の情報』を教えてくれたら、自分もそれに見合うだけの『自分の情報』を相手に伝えたくなる」
人にはもともと、
『他人との良好な対人関係を維持したい』
という基本欲求があるからです。
この欲求に従い『返報性の規範(もらったら返す、にまつわるルール)』を守っていくことで、人は他人との信頼関係を築き、親密な人間関係を維持していくことができます。
人は、他人からの影響を受けずに生きていくことができません。
自分を知るためにも他人は必要。
自分の言動や考えはみんなに受け入れられているか。
仲間として迎え入れられているか。
これほどまでに他人が気になるのは、至って当たり前の感情なのです。
もしも『みんなと違う』と判断されてしまうと、その集合体から排斥されてしまう。
「オレは一匹狼だから関係ない」
と思うかもしれませんが、『他人との良好な対人関係を維持したい』というのは本当に基本的な人の欲求。
かつて集団で獲物を狩り、子育てをし、協力関係なしには生きていくことができなかった原始の時代から続く、生き延びるために人が作り上げていったルールのようなものが『返報性の規範』。
そのための基準となったのが『他人』だからです。
心の奥底に、この感情はどうしてもあるのですね。
ない場合には、残念ながら社会の中で生きていくことが困難となり、どのような形になるかはわかりませんが、排斥されてしまいます。
自分が「大丈夫。問題ない」と思っていても、それを決めるのは周りの他者なんです。
── さてさて、ここでもう一度新人俳優さんと舞台監督さんです。
上記『返報性の規範』を絡めながら振り返ってみましょう。
まずは新人役者さんの『要請(お願い)』。
これは『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』に従い『拒否されること前提のお願い』です。
ですので舞台監督さんは断ります。
では、なぜこの最初のムリな要請が必要なのか?
この要請がなければ舞台監督さんに『断る』という行為をとってもらえないからです。
人の基本欲求は、
『良好な対人関係を維持したい』
ですので、本来人は、
『誰かの要請にはできるだけ応えてあげたい』
と思っているはず。
ですが、この要請はあまりにもムチャ。
なので『断る』。
ここで舞台監督さんの心は、今まで考えてもいなかった方向に動き出してしまうのです。
罪悪感ですね。
新人役者さんがとんでもないお願いさえしなければ生まれなかった感情が芽生える。
-
「彼の要請を拒否してしまった……」
そして続いての新人役者さんの『譲歩』。
『主役をやりたい』の主張を取り下げ(譲歩し)、『チョイ役』に要請を変更。
ここで『返報性の規範』です。
『他人から受けた行為と類似する行為を自分も他人に対して行うべき』
舞台監督さんの心は、見事に翻弄(ほんろう)されていきます。
-
「主役の主張を取り下げた新人君の譲歩に対し、自分は何を譲歩すべきか……? なに? チョイ役でいい? これだ !」
のような感じ。
新人役者さんの『お願い第二弾』の投入は、まさに渡りに船。
舞台監督さんにとっても、非常に都合のいいお願いになったわけです。
ですので、舞台監督さんは『拒否』から『応諾』へと、気持ちをすんなり移行することができた。
そして新人役者さんも『通行人・その4』の役を獲得。
── 丸く収まったかのように見えますが、ここでちょっとストップです。
そもそも、舞台監督さんは新人役者さんに何らかの役を割り振るつもりはあったのか?
相手はズブの素人、新人です。
おそらく当初の予定では、
「新人君には今回、照明係でもやってもらおう」
と思っていた可能性が『大』なのです。
にもかかわらず、なぜ新人役者さんは役を得ることができたのか?

一度断らせたからですね。
そのことにより相手の罪悪感を喚起。
そして、その後に一旦主張を取り下げ『譲歩』の姿勢を見せる。
ここで相手の『同じように自分も譲歩すべきだ』の感情を刺激します。
最後の決め手に、相手が譲歩に使えるコマを差し出す。
それが『チョイ役』。
ここでポイントとなるのは、新人役者さんはそもそも初めから主役になりたいわけではなかった、ということです。
本当に聞き入れてほしかったお願いは、通行人・その4でも5でも何でもいいので舞台に立つことだったのですね。
『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』で大事なのは、
-
『本来のお願いは、最初にするお願いよりも小さな要請にすること』
『本来のお願いは後出し』
つまり、段階を踏むことです。
受け手が一度目の大きな要請を拒否。
その後、相手にとっても応諾するのに抵抗の少ない小さな要請をする。
この段階を踏むことで、
-
『罪悪感を解消』
『相手から受けた行為(譲歩)と類似する行為を自分も返したい(返報性の規範)』
の気持ちが生まれ『第二の要請(本来の要請)』が応諾されやすくなる。
これが『ドア・イン・ザ・フェイス』。
人が持つ『良好な対人関係を維持したい』という基本欲求に訴えかけるテクニックになります。
『ドア・イン・ザ・フェイステクニック』の参考例はこちら!
-
「買うつもりはなかったのについ買いたくなって買っちゃった」
「早く帰りたかったのに、あの人に残業を頼まれると、どういうわけだか引き受けちゃうんだよなぁ」
「なんで僕、この人のご飯の誘いに応じちゃったのかしら?」
「壺を……買わされてしまった……」
悪いことに使ったり壺を買わせてはダメ。
ですが『ドア・イン・ザ・フェイス』はできるセールスマン御用達のテクニックでもあります。
交渉などを有利に進めるにはかなりポイントの高い技法。
本来の『ドア・イン・ザ・フェイス』は二段階なのですが、応用編として活用するのであれば、その回数にこだわる必要はありません。
大きな要請から徐々に小さな要請へ。
最終的に本来の要請が受け入れられればそれでOK。
なのですが、あまりしつこいのはダメです。
お願いの内容云々の問題でなく、人として嫌われてしまいます。
また、同じ人に何度も使えるものでもありません。
いつも同じような依頼の仕方をしていると、薄々感づかれ『それがオマエのやり方か!』とテクニックを使っていることがバレてしまいます。
そのうち相手にされなくなってしまいますのでご注意ください。
また、最初にする大きな要請が、大きすぎるのもダメ。
-
「今度のお誕生日、家買って!(本当に欲しいのはプレステ)」
「はいはい、家ね~」
リアリティがなさすぎると、単なる冗談にしか聞こえません。
その他、より効果を高める条件・参考例等をいくつか以下に挙げていきます。
こちらも参考までにどうぞ。
★ 依頼する側、依頼される側は同じ人で統一
『100円』→『50円』
例えばですが、このような要請の『大』→『小』を、
- 同じ人が2人の違う相手に対して行う
- 同じ相手に対し、2人の人がそれぞれに行う
などですね。
これでは効果は上がりません。
わかりやすく『要請が小さくなった』と相手に思ってもらえることが大事。
同じ人が同じ相手に行うことで、テクニックの効力は発揮されます。
★ 電話・手紙・メールなどより『直接会って』行う

これにはもう一つの意味もあり、『第一の要請』の直後に『第二の要請』が行われることが好ましいとされているからです。
2つの要請を関連付けるためです。
先ほどの新人役者さんも、主役を断られた後、数日してから『チョイ役でも!』と申し出た場合には、受け入れられる可能性は低くなります。
『主役』→『チョイ役』の関連が薄れてしまうからです。
要請『大』から『小』への変化に気づいてもらいやすくするためにも、タイムラグの少ない『直接会って』が効果的なのです。
★ 要請が向社会的なものほど聞き入れてもらいやすい
『向社会的』とは簡単に言いますと、
『見返りを求めない、誰か、または社会のためになること』
献血やゴミ拾い運動や、席を譲る、『ありがとう』と自然に言う、などなど、要するに『道徳的に褒められる行為』的なものです。
相手の存在や言動により、自分自身に変化が現れる理由には、
- 情報的影響
- 規範的影響
の2つがあります。
どちらも依頼や説得に使われる、人の心理に基づいた手法です。
『情報的影響』とは客観的に、あることに対しての情報を伝えることで、その真価などをわかってもらい、相手の変化を促すこと。
例えば購入して欲しい商品の有用性を機能や希少価値などでアピール。
他方『規範的影響』とは、社会的にこうするのが正しいのだ、という部分の提示により、相手に変化を求めていくことです。
『返報性の規範』を利用したテクニックである『ドア・イン・ザ・フェイス』では『規範的影響』が結構重要となってきます。
罪悪感を少なからず喚起する(断るから)その要請が向社会的なものであればあるほど『拒否』することへの抵抗は強くなります。
誰か(または社会)のためになることはわかっているのに断っているからです。
-
「捨て犬・捨て猫の命を救ってほしい。ぜひ1匹だけでも譲り受けてもらえないか?」
この要請にはできることなら応えたい。
ですが、状況によっては簡単なことではないんです。
だから、
-
「うちはペット飼えないんだよ……ごめんな」
となるわけです。しょうがない。
でももうこの人、結構キツイです。
罪悪感が「今日、高級ホテルのビュッフェランチしない?」を断るのとは次元が違うくらい高まってきています。
そこで第二弾。
-
「そうだよな。賃貸だもんな……。
じゃあ、せめて寄付だけでもお願いできないか?
毎月一人千円の寄付で、○○頭の命が救えるんだ」
寄付します!
毎月たかが千円で救えるなら!
となる。
これが初めから、
-
「捨て犬・捨て猫を救うために毎月千円の寄付をお願いできないか?」
とダイレクトにお願いした場合ですと、
-
「いや、毎月っていうのはちょっと……」
となるかもしれません(断ってないから)。
また、違うパターンで、
『毎月千円の寄付』
から始め、
『今回だけ』
とすることでも受け入れてもらえる率は高まります。
どのような場面でも技法に違いはないのですが、より一層相手のモラルに訴えかけるのが『向社会的』な依頼です。
★ バイトのシフトを変わってもらいたい!
- 本当に変わってほしい日: 8月21日(彼女の誕生日)
- その伏線: 8月14日からの1週間
-
「14日からちょっとしたイベントの準備をしたいんだ。1週間、オレのシフト、お前に任せられないかな?」
「いや、ムリでしょ。1週間って、7日間だぜ。長すぎだって」
「まあ、そうだよな。悪かった、つい頼っちゃってごめんな」
→ 何となく『罪悪感』と、この相手の譲歩に対する『自分は何も応えてやれないことへのムズムズ感』発動
「謝んなよ。でも1週間ぶっ続けはオレもキツイわ。悪いな」
「いや、オレも悪いよ。せめて21日だけでも誰かに頼めると本当に助かるんだけどな……」
→ ロック・オン!
「21日だけでいいなら、オレ、変わってやるよ」
→ 応諾・獲得
ここでのポイントは『数字』。
初めの要請『1週間』からわかりやすく『たった1日』への変化が功を奏しています。
★ 値引きしたと見せかけて……
- 本当に売りたい金額: 300円(これでも十分に元が取れる)
- その商品の値段として提示している金額: 1000円
-
「この高級トマト、もう少しお安くならないかしら?」
「いやぁ、これでも勉強した方なんですが……(しばらく値段交渉)」
「奥さんには負けましたよ。じゃあ、半額で持ってってください。他のお客さんには内緒ですよ」
「あら、半額?! なんだか悪いわね。それじゃ、このおミカンも一緒に頂こうかしら」
→ 本当に金額を譲歩するパターン
(大きな要請に当たるのは、初めの値段設定です)
でももともとは300円でも利益の出る設定なので、この時点でも200円の儲け。
しかも『値引きしてもらった』にこちらも応えようと(返報性の規範により)、ついでにミカンもお買い上げ。
「毎度あり!」
★ お母さん、新しいスニーカー買って!
- 欲しいスニーカーの値段: 4900円
- 交渉に使うスニーカーの値段: 9900円
-
「お母さん、クリスマスでいいから、このスニーカー買って欲しいの!1 万円切ってるし!」
「!! 9900円! 1万円切ってるって……100円だけじゃない! ダメ、却下。もうちょっと安いのにしなさい」
→ 拒否、いただきました!
「うーん。カッコいいのになぁ。じゃあ、やっぱりこのくらいの値段が妥当かなぁ」
→『クリスマスプレゼントにはスニーカー』という流れができ、お母さんの心にも『もう少し安いのなら』の譲歩の気持ちが芽生える
「あら、これだってカッコいいじゃない。4900円で、5000円切ってるし」
→ 4900円も5000円より100円だけしか安くないのですが、とりあえず交渉成立!
こちらも値段交渉ですが、先ほどのトマトとは違い、わかりやすい『ドア・イン・ザ・フェイス』。王道です。
★ 自分に対しての使い方もある!
こちらは完全なる『応用編』ですね。
言葉は悪いのですが、使い方を誤れば『ドア・イン・ザ・フェイス』は騙しのテクニックとなるのです。
他人を騙してはダメ。
騙すのは自分だけにしときましょう。
例えば部屋の掃除でも勉強でも、何でもいいのですが、とにかくやる気の出ない時。
まずは他人に対する『ドア・イン・ザ・フェイス』と同じく、自分に対して大きめの要請を設定します。
- 今日の目標『大掃除』!
- 過去問を最後まで解く!
→ うんざり……
もうここはリアルに想像しましょう。
かなり胸が苦しくなってくるかと思います。
「やりたくない……」
ならば、ということで、
- じゃあ、せめてこの部屋だけでも掃除しよう
- 10ページだけでいい、とりあえず少しだけやろう
やるべきことのハードルを下げてあげる。
「このくらいならできるかも。大掃除(過去問全部)に比べれば、こんなのパラダイスじゃないか!」
なぜかやる気も出てくるはずです。
ポイントは「初めに想定してたことより、何て楽なクリア基準なんだ!」と思えること。
★ ボクは彼女が好きだ!
これは一歩間違えると、
「何、あの人。絶対ムリ!!」
ともなりかねませんので、注意が必要。
-
「こ、今度一緒に旅行に行きませんか?」
「行きません。ごめんなさい」
「じゃ、じゃあ、一泊旅行に!」
「それ、同じことですから。行きません!」
「……なら、週末に一緒に映画を観に……」
「行きません!」
「せめて連絡先を……」
「あ、○○先輩! お疲れ様で~す!(去っていく彼女)」
── 恋愛テクニックとして使うには『ドア・イン・ザ・フェイス』は若干弱い。
なぜなら『返報性の規範』に訴えることにより成立するテクニックだからです。
万能ではないんです。
恋愛に使う場合には、他のテクニックとの合わせ技でいきましょう。
まずは相手に自分を知ってもらうことから。
会う回数が増えれば、自然と人はその相手のことが気になってくるもの。
偶然を装ってでも、その回数を増やす。
そして相手自身のこと、興味を持っていること、好み、考え方などを知り、
『僕はあなたと似ています』
ということをアピール(類似性の法則)。
『ドア・イン・ザ・フェイス』が使えるのは、これらの条件がある程度整ってから。
親しくない人の要請より、親しい人の要請の方が受け入れられやすいからです。
『ドア・イン・ザ・フェイス』は非常に優秀なテクニックではありますが、人の心理はもっと複雑。
人の心理をついたテクニックには様々なものがありますが、何か一つだけで完璧に機能するものはありません。
ですが対人関係における人の心理の基本部分は、
『良好な対人関係を維持したい』
ですので、相手を思う気持ちがあれば、自然と相手にもそのことが伝わり、それに対し『お返し』として好意を持たれます。
これは本当。
テクニックは、その薬味的なものです。
対人関係をより良くするために、ぜひスパイスとして活用してみてください。
ドア・イン・ザ・フェイステクニックのあれこれをまとめる!

人の心の自然な働きを利用したテクニック、というと、何となく『ダマし打ち』的な姑息感がありますが、本当は、
『良好な対人関係を築くために、人間の自然な心理に基づいた言動をとる』
なんです。
どうせ何かを買うのなら、納得して気持ちよく買ってもらいたい。
残業させてしまうのは申し訳ないが、できればイヤイヤではなく、快く引き受けて欲しい。
などなど、そのためのテクニック。
ではここでもう一度軽くおさらいです。
まとめていってみましょう。
ドア・イン・ザ・フェイステクニックの流れとポイントは?
-
★流れ
- 初めに断られるような大きな要請(依頼・お願い)をする
→ 相手の拒否
- その後、本来の要請である初めのものよりも小さな要請をする
→ ここが『譲歩』部分
- 要請した側が譲歩したことにより、相手からの譲歩も暗黙に要求
→『返報性の規範』により、拒否から応諾へと変化(相手)
→『良好な対人関係を維持したい』という欲求が根底にあるため
→ 同時に要請を拒否したことへの罪悪感を解消したい、という気持ちも応諾しやすくなる要因に
- 本来の要請は初めの要請より、相手にとって受け入れることへの抵抗が少ないものにする
- 初めの要請があまりにも現実離れしたものはダメ
- 『初めの要請』と『二度目(本来)の要請』が関連づいていることがはっきりわかることが大事
- 同じ人に何度も使うのはNG。テクニックを使っていることがバレてしまうと逆効果に。交渉等の成立は望めません
- 電話やメールなどより直接会って行う方が効果的
- 向社会的、またはモラルに訴えるようなものほど、聞き入れてもらいやすい
- 由来は『shut the door in one’s face』=『門前払い』。
『初めに門前払いをされるようなムリなお願いをする』ことから - 応用すれば、自分自身に対しても使える!
△ただし、万能ではない(他のテクニックと併せて活用することで、より効果を得ることができます)
★ポイント
終わりに……
『心理学』はやたらと言葉が専門的だったり、簡単なことをわざわざ難しく言っているかのような部分もあるのですが、よくよく考えますと、人はみんな『心理』を持っているのですね。
ですので、案外心理学でいっていることは、当たり前のことだったりもします。
そして、当然人はそれぞれなので心理学で『こう』とされていることがすべての人に当てはまるわけではないのです。
いわば『統計学』。
ですが、テクニックを含め、心理について知ることは、必ず何かの役に立ってくれるはず。
皆さまの今後の人間関係がますます快適なものになりますよう、こっそり願っております。
今回も最後までおつき合いいただき、ありがとうございました。
最後に
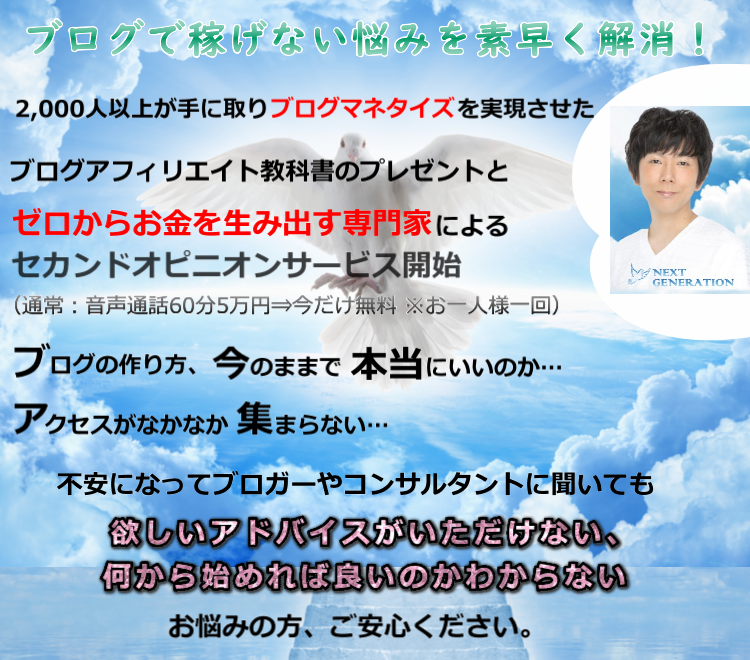
「セカンドオピニオンサービス」と
4万数1000作品の中から優秀賞を獲得した
「動画18時間のブログマネタイズ専用教科書(アフィリマシーン)」を
▶ メルマガ登録者様に無料プレゼント中!
迷っている時間が長いと成功するまでに時間がかかってしまいます。
1日でも早くブログで月収10万円超えを実現しましょう!
ーーー管理人紹介ーーー
齊藤 健(HN:花月)
埼玉県生まれ
Web集客コンサルタント
メンタル障害アドバイザー
ChatGPTマネタイズの専門家
ゼロからお金を生み出す専門家として18歳より活動を開始。
一人ビジネスで億超えを達成し、それを教えたところ数1,000万円稼ぐ実績者が誕生。
現在はインターネットを活用したビジネスを専門に多くの実績者を輩出。
副業からインターネットビジネスを始める初心者のクライアントさんと近い距離で自分メディアにお客さんを集める戦略策定、施策が得意。
自身がメンタル障害で苦悩してきた経験を活かして、メンタル障害からビジネスで圧勝する必勝パターンを研究・ブラッシュアップして自宅を仕事場にしたい人を応援している。
セミナー登壇やメディア出演も経験。
好き:ねこ、昼寝、刃牙、ワンピース
嫌い:上下関係、我慢、梅干し
趣味:動物と遊ぶ、読書、瞑想
LINE公式:https://lin.ee/i7sXyFe
LINE公式限定:旬な話題やAI関連のマネタイズ方法などを配信中。


